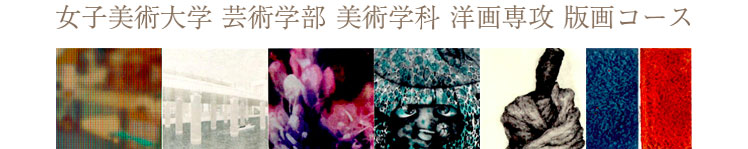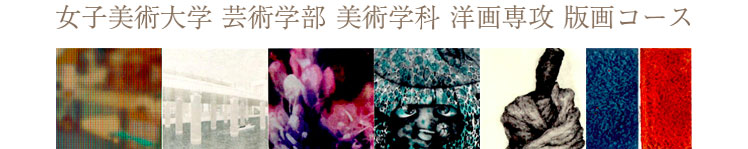|
BC4000
|
印章の使用(メソポタミア) |
|
100
|
中国(後漢)の辞書『説文解字』に紙についての記述あり |
|
105
|
中国(後漢)で蔡倫が「紙」を発明 |
|
610
|
墨、絵の具、製紙法が高麗僧・曇微によって日本に伝わる |
|
751
|
タラスの戦い(唐 対 サラセン) サマルカンドに製紙法が伝わる |
|
770頃
|
現存する日本最古の木版印刷「百万塔陀羅尼経」法隆寺 |
|
868
|
現存する最古の版画『釈迦説法図』(金剛般若経)扉絵(中国・敦煌) |
|
11世紀頃
|
中国に陶版を彫刻して焼いた印刷版の記録 |
|
1151
|
スペインに製紙法が伝わる |
|
13世紀初頭
|
朝鮮に金属活字最初の記録 |
|
1276
|
ファブリアーノ(イタリア)に製紙工場 |
|
1370〜頃
|
プロタの版木 |
|
1391
|
ニュンベルグ(ドイツ)に製紙工場 |
|
1445
|
グーテンベルグが活版印刷を発明 |
|
1448
|
グーテンベルグによる『42行聖書』の印刷を開始 |
|
1455
|
活字版『42行聖書』出版 |
|
1520年頃
|
ネーデルランドのルーカス・ファン・ライデンが銅版でのエッチングを始める |
|
16世紀
|
多色刷り木版が西洋で登場 |
|
1643
|
ルードヴィッヒ・フォン・ジーゲン、メゾチント作品を発表 |
|
1665
|
ニュートンがスペクトルを発見。色の三原色の礎となる。 |
|
18世紀
|
錦絵版画隆盛(日本) |
|
1732
|
ジャック・クリストフ・ル・ブロンが3原色をメゾチント版で刷り重ね色の再現に成功 |
|
1783
|
司馬江漢が日本初のエッチングを制作 |
|
1798
|
ゼネフェルダー、石版画の発明 |
|
18世紀末
|
イギリス、フランスで木口木版が盛んに |
|
1800
|
ゼネフェルダー、石版術の特許を取得 |
|
19世紀
|
フランスでリトグラフ盛んに |
|
1801
|
トーマス・ヤングにより赤・緑・青(青紫)の色光を感じ取る神経の存在が唱えられる |
|
1837
|
ゴドフロア・エンゲルマンが3原色に墨版を加えた4色刷りによる色彩印刷の方法を完成しリトカラー印刷の特許を得る |
|
1839
|
ダゲレオタイプ発表。写真の始まり |
|
1882
|
マイセンバッハが「網点分解」の特許を取得 |
|
1898
|
デジョン郊外で「プロタの版木」見つかる |
|
1904
|
山本鼎が木版画「漁夫」を発表。日本の創作版画の始まり |
|
1930
|
網目スクリーンにかわるコンタクトスクリーンがコダック社から発売 |
|
1960年代
|
シルクスクリーン盛んに |