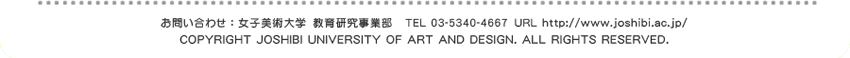吉武 それでは、そろそろ終了時間の12時が近づいてきました。どんな質問でも構いません。何か質問がおありであれば手を挙げて。佐野学長どうですか。
佐野 ありすぎてちょっと言えません。
土谷 今日はこのご対談の記録担当として、お話を聞かせていただいておりました。土谷と申します。ありがとうございました。お話を伺って、ちょっとドキッとさせられたのが、我々がそういう障害者のアートを見る時、いびつさを求めているということを言われたことです。確かに、「面白いな」とか、ある種の優越感みたいなものが自分の中にあったかもしれないとハッとしましたが。さらに進んで、「アール・ブリュット」の作品を見ていく中で、先生方がお話になっていたように、「頭で考えていることはたかがしれている」と言われたことに、これからの社会に対するすごいヒントがあると思いました。この人たちの作品を見て、何を学んでいったらいいのかというのを少し教えていただければと思うんですが。
野見山 僕は自分でね、壇上に立ちながら、何で自分はここにいるのかが不思議でならない。これだけ、僕は長年絵を描いてきても、「絵」はこういうものであろうという正体を、どこまで行っても突き詰められないでいる。僕らとはまるっきり違う人たち(普通の生活が出来ない、障害者の人々)の絵が、僕らの胸を打つのだろうか?と不思議でしょうがない。絵以外の世界だったら、彼らは健常者の人たちと同様な生活に入っていけないのだけど、なぜ、絵の世界となると僕らの胸を打つのか。その疑問の先には、僕らが突き詰めるべき絵という世界の何か大きな意味が、きっとあると思うんですね。
つまり、彼らの描く絵の中には、僕らが忘れている、根源的で純粋なものが現れている気がする。現実では存在しないかもしれないけれども、夢の中で見ているものが、彼らの作品の中に如実に示されているんですね。それらは、現実に僕らが視覚を通して見たことがない世界を提供している。なぜ、そういう世界を描けてしまうのか不思議でならない。作品がいい悪いとは別として、僕らが描いている「絵」は一体何なんだろう?という見直しの問題にぶつかるんですね。
何で僕らは彼らの作品を"異常"だと思わなきゃならないのか。彼らの頭の中身に一体どういう世界があるのか。不思議でしょうがないんですね。本当はこの「アール・ブリュット」の人たちに直接聞いてみたいのだけど、彼らには答えられない。答えるだけの思考力が彼らにはない。むしろ、そういう思考の欠落がこのような作品を生んでいるのですから。
入江 僕もなぜ、「アール・ブリュット」に惹かれるかと言われれば、常識や秩序にとらわれない自由さを感じて、逆に、自分が「絵」という常識にどれだけがんじがらめになっているかということを逆に改めて感じる、そういうところが惹かれる理由だと思います。
ただ、さっきも言ったように、それが作品の価値としてもつかもたないかっていう観点もとても大事なことです。熊谷守一(※33)っていう人をみなさん、ご存知だと思いますが、子どもみたいな絵を描く人です。やっぱり、彼の絵は価値がもつなあっていう感じを受けるわけです。熊谷守一のように作品の価値が続く絵と、続かない絵との違いはどこかなっていうことを考えた時に、やっぱり、そこにはその本人の人生体験の積み重ねがあるかどうかが大きな違いかと思う。熊谷守一は、仙人と言われるような生活をしていた。自分の家の庭にむしろを敷いて、アリとにらめっこをするような生活をしていたと言われている。長い一生の間に、苦しみやもがき、実にさまざまな人生体験を積み重ねて出来た覚悟のようなものを彼から感じる。やっぱり「絵」というものの中には、単に自由だからいいというんじゃなくて、描く人の人生体験とのつながりが問われる。自分の一生の積み重ねと、絵とはつながりがあり、それが絵の価値を続かせるかどうかという問題に大きな関係があるのではないかと僕は思っています。
佐野 「面白うてやがて悲しき鵜飼いかな」(※34)という句がありますよね。私はあれを思い出しました。どうしても最後は、悲しい。面白くも楽しくもおかしくもなくて、私は、最後はやっぱり一つひとつ見ると悲しくなるんです。絵の評価などは、先生方にお任せして、いい作品はいい作品として、皆さんにごらんいただければいいと思います。作っている人間が、健常者でもなければ障害者でもない、いわゆる人間として認めてもらいたい。その人間がどういうふうに生きていくかという、絵を描く前のところを一生懸命私たちが見てやるというか、一緒になって生活していくべきじゃないかと今思っております。
吉武 どうもありがとうございました。
ちょうど時間がいい時間になりましたので、そろそろ終了とさせていただきます。このお二人に拍手をお願いします。新しい視点の発見や、心に残る言葉をたくさん聞けたように思います。先生方、どうもありがとうございました。
![]()
※33 熊谷守一(1880年4月2日 - 1977年8月1日)
岐阜県生まれ。東京美術学校出身の画家。「画壇の仙人」と称される。
※34「面白うてやがて悲しき鵜飼いかな」
松尾芭蕉の俳句。須磨、明石まで足を伸し、大津でしばらく滞在し、長良川の鵜飼を見に行った際、うたった俳句である。