 |
 |
 |


|


     
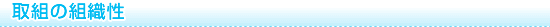
(1)取組の意義と価値の共有
美術は、自己発見の手法を活用でき、問題解決策を提起できる教育の特性を有する。美術教育の役割を踏まえ、他者への配慮など美術分野の切り拓くべき道標を立てる。
(i)障害者への社会参画・自立支援
例えばマップ作りの中で得た成果をWeb上に展開することで、寝たきりの障害者の方でも新たな視点から自分の存在(ポジショニング)を再発見・認識し社会参加できる。
(ii)他者への理解
他者・自己を対象に、例えば商店と買物客、環境問題でもゴミを出す側と回収する側で立場が異なることを双方向で理解する。
(iii)行動の動機付け
自分がアクションを起こすことで周りからの反応がある。それによって自分の行動を振り返ることができ次の行動への自発的起点となる。「いきいきプロジェクト」の下には、テーマごとにプロジェクトチームが活動し取組の輪を拡げる。本プロジェクトは大学、短大、専攻科という全学的な授業展開の取組に加え、課外活動や学習活動を精査し専門教育にリンク付け、目的を明確化する過程から始まった。
(2)学内の支援体制
運営を支援するため、学長の下に「ファシリテーション教育推進センター」を設け、運営支援の窓口とし、研究所、事業課、NPO等とプロジェクトチームの教職員が協働し全学で取組を実施する。予算措置根拠等経費面を含め全学支援、推進体制を整備する。
|
|
| |
|
|
|