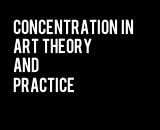CATP 講師
芸術表象専攻の講師陣
藤原えりみ
足立元
リンダ・デニス
畠中実
福住廉
浜田涼
丸橋伴晃
井上文雄
小林晴夫
三田村光土里
渡抜亮
滝沢恭司
天野太郎
黒瀬陽平
良知暁
粟田大輔
仲俣暁生
城戸朱理
及川卓也
太田泰人
藤原えりみ / Erimi Fujiwara
「アート・ジャーナリズム概説」を担当することになりました藤原です。私は大学で美術史・美学を学びましたが、思うところあって研究者の道を選ばず、美術関係の記事執筆・翻訳・編集の仕事にたずさわることになりました。西洋美術史から現代美術までを仕事のフィールドとしていますが、日本美術や他の地域の歴史・文化、さらには漫画やアニメなどのサブ・カルチャーにも深い関心を寄せています。
みなさんは、「アート・ジャーナリズム」と聞いてもピンとこないのではないでしょうか? なんだか難しそうと思われる学生さんもいらっしゃることでしょう。けれども、この講義では、造形表現と言葉の関係、つまり「表現されたもの/表現した人」と「それを分析・解釈し、他者に伝達するための言葉」との関係について、現在に至る流れを整理していきたいと考えています。
ジャーナリズムの誕生はマスメディアの誕生と期を一にしています。それは19世紀のこと。ですが、美術を語る書き記された言葉が生まれたのはもう少し前、16世紀のイタリアでした。現在では、美術をめぐる言葉はいくつかの領域(学問としての研究論文、美術評論(美術批評)、アート・ジャーナリズム)に分かれていますが、16世紀の時点ではまだそれらは区別されていない状態でした。
では、なぜ、研究論文と評論とジャーナリズムという区分けが生まれたのか、また、そのそれぞれ現在ではどのように異なっているのか。それは歴史の変遷や社会の変化と大きく関わっています。たとえば、日本には明治時代になるまで「美術」という言葉も概念もありませんでした。近代化が急速に進む社会のなかで、今でいう「絵画」や「彫刻」、「日本画」という言葉や概念が形成されていったのです。
16世紀のイタリアから、19世紀のフランスや日本を経て現代にいたる時間を、みなさんととともにゆっくりと旅をしながら、「美術作品と言葉がどのように結びついてきたのか」あるいは、時には「離反し合い、その葛藤のなかから新しい表現がどのように生まれてきたのか」を、一緒に考えていきたいと思っています。
アート・ジャーナリスト。
担当科目 : アートジャーナリズム概説(院)/現代文化論
関連リンク : twitter